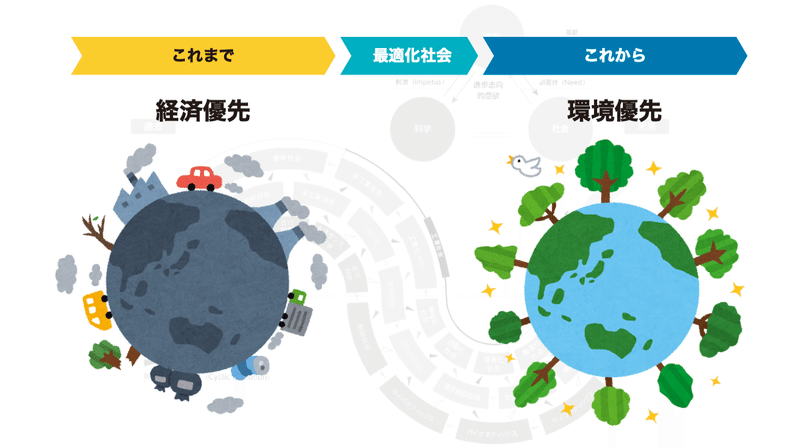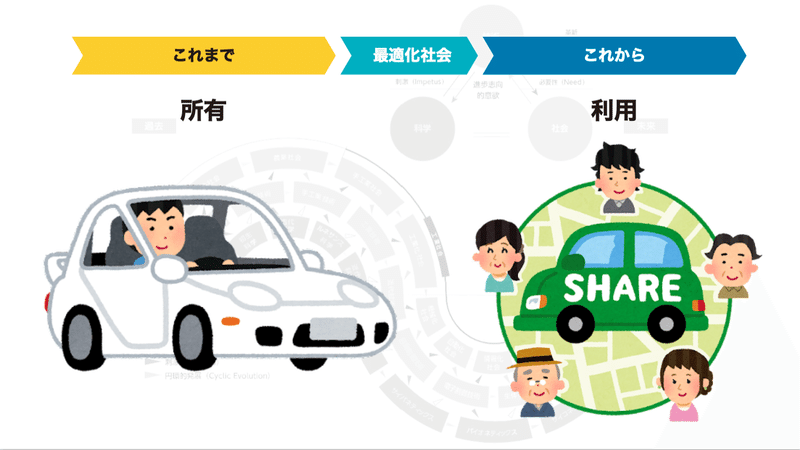無い物ねだり』という言葉があります。
自分が持っていない物を欲しがるという意味ですが、欲しくなる物って、だいたいは『持っていない物』ですよね。
すでに持っている物を欲しがることはないので。
そういう意味では、二重表現とまでは言いませんが、『違和感を感じる』みたいな語感です。
ともあれ、お金とか、恋人とか、自分にあった仕事とか……
お悩み相談の大半は『無い物ねだり』だったりします。
『無いから欲しい』の堂々巡りです 😊
しかし、『無い』にフォーカスすると、残念ながら望みはかないません。
現実世界は自分が『当たり前』だと思っている通りになるので、「実際に無いから困ってるんだよ」と強く思えば思うほど、願望実現が遠のく理屈です。
これって、ある種の逆説だと思います。
一旦「無いから欲しい」と思わせておいて、「そう思うからかなわない」なんて……
ずいぶん意地悪な展開です。
そして、この展開が自然に起こるからこそ、人の悩みは尽きないのかもしれません。
悩みって、簡単にはわからない謎解きみたいなものですね 😊
一方で、「願いは心に浮かんだ時点で、かなっている」とも言われます。
自己啓発やスピリチュアルの分野では、いろんな人がいろんな説明をされていますが、言われていることはほぼ同じ。
『無い』にフォーカスするのではなく、『有る』を意識しましょう、という導きです。
ただし、理屈っぽい解説が好きな人もいれば、ふわっとした語りが好きな人もいます。
そのあたりは単純に『あう/あわない』の問題ですが、わたしは理屈寄りなので、以下のような説明がしっくりきます。
人が何かを『欲しい』と思うのは、それを手に入れた時の喜びの記憶(に類する感情)が自分の中に『有る』からです。
そして、喜びのマックスは実際に手に入れた後ではなく、手に入れる直前(手に入っていない最後の瞬間=期待の最大値)に訪れることが、統計的にわかっています。
アイスを味わっている時も幸せですが、フタをあける時のワクワク感の方が感情の揺れは強いということ 😊
だとしたら、『欲しい』の延長線上に、その期待の最大値は『有る』ことになります。
その感覚をくり返しイメージしていれば、願いはかないやすくなるし、たとえかなわなかったとしても、願いにまつわる喜びをすでに味わい尽くしているという道理です。
勝利の瞬間を思い浮かべるイメージトレーニングも、日本古来の『予祝』という習慣も、理屈としては同じ。
羽生結弦さんが、ソチオリンピックに向かう飛行機の中で、泣いていた話は有名ですね。
実際に金メダルを取った時の感想も
「飛行機の中でイメージしすぎて、飛行機のほうが感動しちゃいました」
でした 😊
「そうなった時の感情をあらかじめ味わうことが、願望実現の秘訣」と言われる由縁です。
そうなることを潜在意識レベルで『当たり前』に感じている人が強いんですね。
そのためのコツは、善き言葉を使う人と一緒にいることです ❣️

毎日更新しているnoteもどうぞ ▼▼▼


歴史の英知を共有していきましょう!